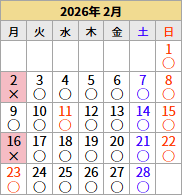萬翠荘 ホームに戻る|俳句の殿堂TOP|~俳句の殿堂~ 煌星俳句会
煌星(コウセイ)
結社理念

誓子の根源俳句、利彦の自然美詠唱を受け継ぎ、
- 1)本質把握
- 2)感動第一
- 3)新想深意
主宰者

石井 いさお(イシイ イサオ)
昭和16年三重県生まれ。
三重大学を卒業。高校教員を38年。山口誓子に根源俳句を、松井利彦に評論の書き方を学ぶ。
平成16年煌星を刊行。この間『俳壇』で俳句と随想を一年間、『俳句界』の選を一年半勤める。
連絡先
住所
〒510-1253 三重県三重郡菰野町潤田772
〒510-1253 三重県三重郡菰野町潤田772
FAX
059-393-4529
059-393-4529
主宰の100句
| 1 | 磯風を翼に溜めて春の鳶 |
|---|---|
| 2 | 豆を撒く闇に手応へなかりけり |
| 3 | 海女小屋の焚火明かりに繕へり |
| 4 | 船笛は漁師の言葉鰆船 |
| 5 | 老藤の万力棚を締めつける |
| 6 | 小走りになれば小走り遠足児 |
| 7 | 静止画の動画となれる落花かな |
| 8 | 磯嘆き十尋の深み吐き尽くす |
| 9 | 棒として引き上げらるる疲れ海女 |
| 10 | 渦潮や白き絵具を奔放に |
| 11 | ビブラートつけて鳴き継ぐ揚雲雀 |
| 12 | 海女潜り遅れて潜る命綱 |
| 13 | 伊那谷の深きをえぐり雪解水 |
| 14 | 垂直に入り垂直に海女浮かぶ |
| 15 | 繫留の船と共揺れ花筏 |
| 16 | 曇天につかへ雲雀の横滑り |
| 17 | ちぎれとぶ声を交して若布舟 |
| 18 | 火の筵捲り上げつつ野火走る |
| 19 | 朝の日を絡めとつたる白魚網 |
| 20 | 島島を置石にして瀬戸の春 |
| 21 | 瀬音に寝瀬音に目覚む芽木の宿 |
| 22 | 岬に湧き岬に消えゆく春の鳶 |
| 23 | 揚雲雀天に経線引き続け |
| 24 | 押し合うて流水己が位置定む |
| 25 | 揚雲雀雲に音符を撒き散らす |
| TOPへ | |
| 26 | げんげ田が囲む明日香の后陵 |
| 27 | 火振漁黒子のごとく人動く |
| 28 | 砂の色残して乾く千鰈 |
| 29 | 祭笛一つうなづき吹き始む |
| 30 | 蛍死し闇の詰まれる蛍籠 |
| 31 | 噴水や濡れたる風の落ちてくる |
| 32 | 名峰が研ぎ出す川に鮎を釣る |
| 33 | 羅の重なるところ翳のあり |
| 34 | 揚花火次のページのめくり咲く |
| 35 | 百丈の風を放ちて滝落ちる |
| 36 | 水音を筬として滝の糸紡ぐ |
| 37 | つばくらめ雲を啄み下りてくる |
| 38 | 絢爛を解きて素木の祭鉾 |
| 39 | 天降る滝風を巻き込み落下せり |
| 40 | 土用波海傾けて崩れけり |
| 41 | 緩みゐず張りすぎてゐず蜘蛛の糸 |
| 42 | 伊勢湾を白塗りに消す大夕立 |
| 43 | 鳥の声沁みゐるテント畳みけり |
| 44 | 祭り笛角度整へ吹き始む |
| 45 | 潮痩せの海女に重たき鮑桶 |
| 46 | 田の水を叩いて怒る水喧嘩 |
| 47 | 夕焼けをワインに溶かし乾杯す |
| 48 | 大西瓜まづ目線にて切つてをり |
| 49 | 撒く餌に紅盛り上がる田の金魚 |
| 50 | 豊かなる水を束ねて鵜飼かな |
| TOPへ | |
| 51 | 焼印を押したる阿蘇の牛冷す |
| 52 | 競べ馬脚に浄めの塩を掛く |
| 53 | 滝上る鮎全身をばねにして |
| 54 | 雪渓の裾に真白な水芭蕉 |
| 55 | 解禁の硬き水より鮎を釣る |
| 56 | 登山バスお花畑が停留所 |
| 57 | 山霧に重みのありて山下る |
| 58 | 吸ふ息も哭いてゐるなり村歌舞伎 |
| 59 | 水落す音に一村暮れてゆく |
| 60 | 山の音山に鎮もり秋深む |
| 61 | 短日や山は光を斜め切り |
| 62 | 十百の岬を掛けて鷹渡る |
| 63 | 添水聞く心の中を水流る |
| 64 | 消えゆきて崩れ字を書く大文字 |
| 65 | 輪中村時雨霞みの方三里 |
| 66 | 風の私語絶ゆることなし芒原 |
| 67 | 応援の声回りゆく運動会 |
| 68 | 島島を湾に嵌め込む水の秋 |
| 69 | 先づ風の流してゆけり風の盆 |
| 70 | 窯出しの茶器も冷やせる紅葉風 |
| 71 | 日の落つる山かはりたり日脚伸ぶ |
| 72 | 木の実落つ山に一つの音加へ |
| 73 | 水の板延ぶる琵琶湖や月今宵 |
| 74 | 一村が虫籠となる虫しぐれ |
| 75 | 稲妻は神のフラッシュ闇を撮る |
| TOPへ | |
| 76 | 水鏡割つて着水飛来鴨 |
| 77 | 鳴く虫の渾身腹も波打たせ |
| 78 | 田を一つ裏返したる蓮根堀 |
| 79 | 桐一葉序の舞二の舞三の舞 |
| 80 | 冬波の荒きを曳けり地引網 |
| 81 | 身を置けば窯場に山の冬の声 |
| 82 | 水面を八つ裂きに吹く北颪 |
| 83 | 千枚の障子明りや白河郷 |
| 84 | 冬の田を刃金剥がしに遺跡掘る |
| 85 | 向きを変へ鴛鴦色を回したり |
| 86 | 風に乗り風を隼超へて飛ぶ |
| 87 | 広き湾牡蠣の漁師は庭と呼ぶ |
| 88 | 銀色の風の吹き抜く樹氷林 |
| 89 | 紺天を一刀断ちに刺羽飛ぶ |
| 90 | 俗界の音を断ちたる雪囲 |
| 91 | 天空の冷え持つ凧を地に下ろす |
| 92 | この島の裏側もまた牡蠣筏 |
| 93 | 注連を綯ふ藁の強弱知り尽くし |
| 94 | 凧落ちる風の呼吸に抗ひて |
| 95 | 竹馬の後ろかぶりの帽子かな |
| 96 | 若水や地球は水の満つる星 |
| 97 | 風神と綱引き連凧高揚る |
| 98 | 先頭が揺れ連凧の竜尾揺る |
| 99 | 遊びたき方へ遊ばせ凧揚げる |
| 100 | 卒業の答辞きっちり折り畳む |