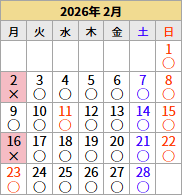萬翠荘 ホームに戻る|俳句の殿堂TOP|~俳句の殿堂~ 風樹
風樹(フウジュ)
結社理念

こころの写生を基本姿勢とする。真の写生とは、詠おうとする対象(もの)のいのちを写すことである。その為には、感覚を駆使するのは勿論だが、その感覚にプラスするのは作家としての第六感である。俳句の正道は、“生きる証”を求道するにある。
観て、感じて、描くという作家三原則を忠実に行い、断じて言葉遊びをしないことだ。
俳句は、“ことばの彫刻なり”
主宰者

豊長 みのる(トヨナガ ミノル)
昭和6年10月28日生まれ。
山口草堂門「南風」編集同人。昭和61年1月「風樹」創刊主宰、現在に至る。
【句集】
『幻舟』『方里』『一会』『風濤抄』『阿蘇大吟』『北垂のうた』『即今』『天籟』『天啓』『天望』
【評論集】
『俳句逍遥』 編著『室生犀星』『21世紀の俳人・豊長みのるの世界』自解100句選『豊長みのる集』
四季別句集『精華』上・下『秀句の風姿』風樹作家百二十人 他多数
連絡先
住所
〒560-0021 大阪府豊中市本町4丁目8-25
〒560-0021 大阪府豊中市本町4丁目8-25
FAX
06-6857-3590
06-6857-3590
主宰の100句
| 1 | 海峡の星みな粗き余寒かな |
|---|---|
| 2 | 三月や日を載せてくる花車 |
| 3 | 長閑さのはては曇りぬ離れ礁 |
| 4 | 春暁や阿蘇寝釈迦山茜曳き |
| 5 | 花曇り泉に斧を浸しあり |
| 6 | 終雪や白樺の幹片濡れて |
| 7 | 鷲上げて流氷の天荒るるなり |
| 8 | 春愁のそぞろにゆるむ旅の帯 |
| 9 | 暮れて野火風の姿となり奔る |
| 10 | あめつちの大きしづけさ種下ろす |
| 11 | 掌のくぼの寄居虫貌出す沖明り |
| 12 | 鳥雲に入りて淡海の曇りかな |
| 13 | 初蝶のあたふたと目の高さかな |
| 14 | 花すもも女人のことば噎ぶなり |
| 15 | 国後やロシアたんぽぽ絮とばす |
| 16 | 徂く春を外に出て行き処なかりけり |
| 17 | 雪虫や瞼閉づるはあたたかき |
| 18 | 鳥雲におほかた抜きし墓の草 |
| 19 | 刻無しの鐘が鳴りつぐ遍路みち |
| 20 | 峭崖や花しろしろとして散らず |
| 21 | 穂高いま雲吹きおとす立夏かな |
| 22 | 雲の峰おもてを上げて歩むべし |
| 23 | 死ぬ日まで炎天の野を蝶舞へり |
| 24 | 夕焼のあなたへ舟を漕ぎ出でし |
| 25 | 七月の北斗崖なす野の別れ |
| TOPへ | |
| 26 | 夜蟬落ちて浮足闇をあるきけり |
| 27 | 尺蠖や来し方くらき峠口 |
| 28 | たましひの抜けて空蟬かろきかな |
| 29 | はんざきの世捨ての貌が水の底 |
| 30 | 緑陰にたましひ透きて人禱る |
| 31 | 深山朴日の一塵もまとふなし |
| 32 | 花あふち逢魔が時を風起る |
| 33 | 風神の色めきたてる牡丹かな |
| 34 | 死火山に月照りいでぬ青芒 |
| 35 | 睡蓮の揺るると見れば水ありぬ |
| 36 | 洞然と朝の天あり蓮ひらく |
| 37 | 花紫蘇を虻の搏つ音卒中死 |
| 38 | 向日葵の光輪眩む天地かな |
| 39 | 玫瑰や親潮といふふかき紺 |
| 40 | 水打ってかの世から風来りける |
| 41 | 風に草靡くは秋のなびくなり |
| 42 | 寺を出るひとりひとりに秋の暮 |
| 43 | 秋高しふさぎの虫を野へ放つ |
| 44 | 母は背に負ふべくおはす鰯雲 |
| 45 | 銀河から船現はるる港町 |
| 46 | 野分過ぐともづな水に垂れ弛み |
| 47 | 着るものの終を白とす雁渡し |
| 48 | 紅茸や山彦一つうしろより |
| 49 | 濯ぎ女に垂るる藤の実妻籠宿 |
| 50 | 内鳴って黍ひとむらの風立ちぬ |
| TOPへ | |
| 51 | 稲は穂に火の国は雲熟るる日ぞ |
| 52 | 鳥兜人は死なずば生くるのみ |
| 53 | 敗れたる国のからりと曼珠沙華 |
| 54 | 白菊のほとりの暮色かりもがり |
| 55 | 旅に在れば帰る家なし草紅葉 |
| 56 | 桐一葉水中の日のゆらめきぬ |
| 57 | さり気なく枯るる生なり藪からし |
| 58 | 下り鮎逢かは日射しそめにけり |
| 59 | 人はみな帰る家あり雁の秋 |
| 60 | 桐一葉ふと好日を怖れけり |
| 61 | 水の香をはなれてたかき帰燕かな |
| 62 | はらはらと豊年雀天降り来る |
| 63 | 流燈を放つわが掌の暗くなる |
| 64 | ひらきたるてのひら白し終戦忌 |
| 65 | 厠出てすとんと釣瓶落としかな |
| 66 | 鐘撞くや万相うごく露の中 |
| 67 | 秋の声振り向けば道暮れてをり |
| 68 | 生くるとはいのち濃きこと天の川 |
| 69 | 雁渡し砂丘は生きて砂奔る |
| 70 | 流燈を点せし貌の揺れてをり |
| 71 | 短日の一大交響楽了る |
| 72 | 鉄いろに川は流れて年逝けり |
| 73 | 大寒の結界塵も立たずなり |
| 74 | 天狼の牙かつかつと闇凍る |
| 75 | 冬銀河荒寥として澄めりけり |
| TOPへ | |
| 76 | 雪起し盤石山の声こもり |
| 77 | 寒雷の海昏みたる濤ころし |
| 78 | あたたかく初雪降れり母の国 |
| 79 | 雪女郎振り向きて眉なかりけり |
| 80 | 吹雪く夜の寝ても手を組む胸の上 |
| 81 | かいつぶりいつ浮かみても風の音 |
| 82 | 人入れぬ葷酒不許門雪降りをり |
| 83 | 眉剃ってしらむ鏡奥雪をんな |
| 84 | きのふ見し山を越えをり初しぐれ |
| 85 | 断崖にひろふ鷹の羽雪曇り |
| 86 | 雪明り天金の書のにほひけり |
| 87 | 青天を鷹の逆落つ海あかり |
| 88 | 鳰鳴いて湖北は星の降りにけり |
| 89 | 冬の蜂日を得しものは力抜き |
| 90 | 人日のけふ禅定に入りにけり |
| 91 | 寒牡丹素心しづかに坐りたる |
| 92 | 仮の世の日向がありて返り花 |
| 93 | 水仙に死の薫香を焚きにけり |
| 94 | 忘却やうす雪しづむ水の中 |
| 95 | 海神の崖に年立つ怒濤かな |
| 96 | オリオンの楯かうかうと年動く |
| 97 | 和歌の浦や四日の磯の忘れ潮 |
| 98 | 鈴の音して玄関に礼者かな |
| 99 | 雲割れて日矢のさしけり仏の座 |
| 100 | 初鶏の刻つげてなほ風にあり |